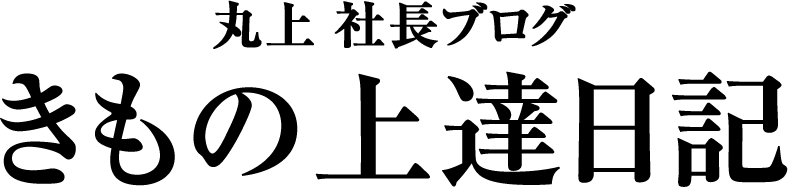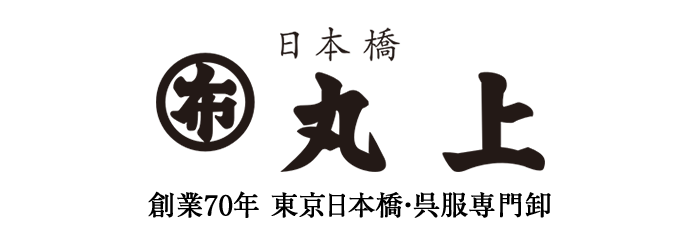先日、ある仕入先の後継者の方が当社にご来社くださいました。「丸上のDXの取り組みを教えてほしい」とのことで、これまでの試行錯誤を踏まえて、実際の導入事例や考え方をお話ししました。
思い返すと、僕が丸上に入社したのは今から20年前。当時、社内にはパソコンが3台しかなく、棚卸しもすべて手書きでした。前職が日本IBMだった僕にとっては、正直かなりのカルチャーショックでした。パソコンがなければ仕事にならない──そんな価値観でいたので、呉服業界の“アナログさ”とのギャップに驚いたのを覚えています。
だからこそ、後継者にありがちな「前職の常識をそのまま自社に持ち込む」という落とし穴もよく分かります。でも、デジタル化は“目的”ではなく“手段”です。大切なのは、現場の業務を理解したうえで、少しずつ最適な形に変えていくこと。無理に大きな変革をしようとすると、現場は混乱し、逆に頓挫してしまうリスクがあります。
僕が心がけてきたのは、「改善を約束すること」。デジタル化の導入によって、社員の負担が軽くなり、労働環境が良くなる。その先にあるのは、生産性の向上と、働きやすい職場です。こうした“未来像”を共有しながら、少しずつ、一緒に進めていくことが大切だと思います。
そして、使っていくうちに社員から「こういう使い方ができるんじゃないか」という新しい発想が生まれてきます。そのとき、DXは“現場からの提案”として自走し始めます。トップダウンではなく、ボトムアップのDXへと変わる瞬間です。
また、DXを進めるうえでは、社員とのコミュニケーションを増やすことも重要です。「導入すること」以上に、「信頼されること」が成果を左右します。「この人が言うなら、やってみよう」と思ってもらえるかどうか。技術以上に、“人と人との関係性”がDXの成否を決めると感じています。
僕自身、人は基本的に「これまで通りでいい」と思ってしまう生き物だと思います。でも、時代はどんどん変わり、お客様の価値観も多様化しています。その変化に対応するためには、自分たちも柔軟に変わっていかなくてはなりません。変化に挑む仲間を少しずつでも増やしていくこと──それがDXの第一歩です。
最初に勤めた会社が、その人の“当たり前”になります。だからこそ、お互いの価値観のギャップを理解し、すり合わせながら進めていくことが大切です。
ちなみに、スマホが普及していて、誰もがオンライン接続された端末を持っている時代になりました。また20年前と違って、中小企業でも手軽に始められる便利なサブスクリプション型のツールがたくさん登場しています。必要な機能を少しずつ導入していける時代です。
もし、和装業界でDXに悩んでいる方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。