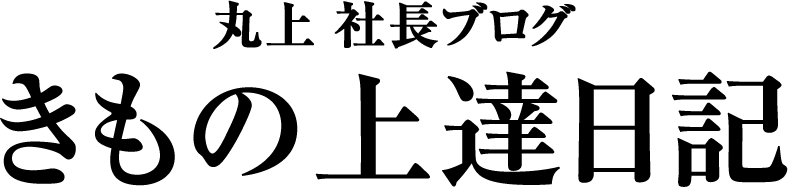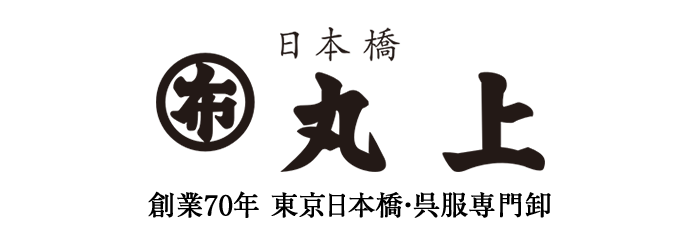今日5月29日は、「ご(5)ふ(2)く(9)」の語呂合わせから生まれた「呉服の日」です。着物業界に身を置く僕たちにとっては、和装文化の魅力をあらためて見つめ直すきっかけになる日です。
ところで、みなさんは「呉服」と「着物」の違いをご存知でしょうか?日常ではあまり意識されない言葉かもしれませんが、意味が異なります。
「呉服」とは、本来は反物や和装用の布地を指す言葉です。もともとは中国の「呉」という国から伝わった絹織物が語源で、江戸時代以降、日本でも絹の反物全般をこう呼ぶようになりました。現在では、反物や和装小物全体、さらには業界そのものを指す言葉としても使われています。着物専門店が「呉服屋」と呼ばれるんです。
一方の「着物」は、その呉服(反物)を仕立てて完成した衣服のこと。つまり、呉服は“素材”、着物は“完成品”と捉えるとわかりやすいと思います。
この違いを知っているだけでも、和装への理解がぐっと深まると思います。
せっかくの呉服の日。けれど、コロナ以降はこの日を活かしたイベントや取り組みが減ってしまっているのが実情です。着物は不要不急のものと思われがちですが、だからこそ「特別な日の装い」としての価値があります。
今日という日を、僕たち自身がまず見つめ直して、来年には、「呉服の日にこんなことをやったよ」と胸を張って言えるような、小さくても何か行動を起こしたいと思います。